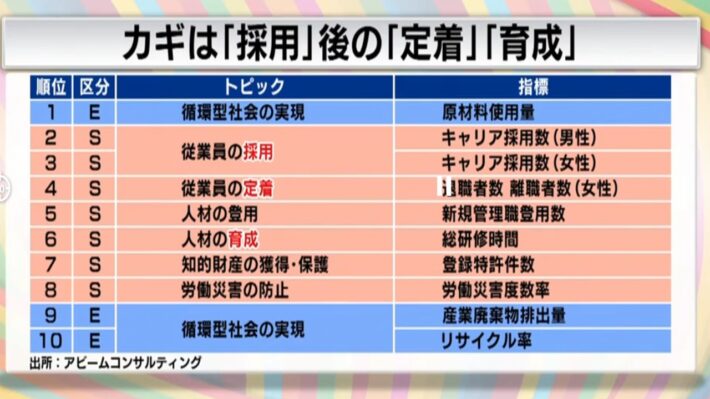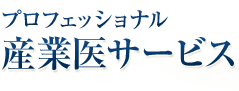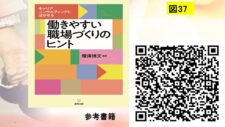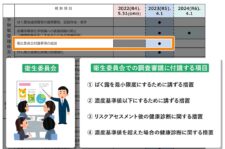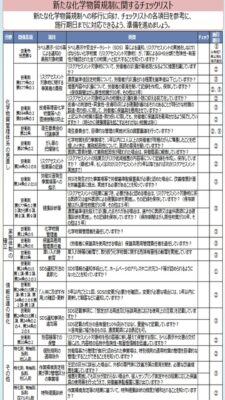2019年時点で既に「キャリア形成サポートセンター」を紹介済です。
2023年度にキャリア形成サポートセンター(通称キャリサポ)はキャリア形成・学び直しセンター(通称キャリガク)へ、更に2024年度にはキャリア形成・リスキリングセンターに名称が変更となっています。
そのキャリア形成・リスキリングセンターが、ジョブカード普及サポーター企業を紹介しています。
ジョブカード普及サポーター企業とは、「ジョブ・カード」を活用して、求職者に対する採用面談、在職者へのキャリアコンサルティング、雇用型訓練の実施、および在職者への実務経験評価等を実施する企業や団体のことを示し、企業や団体側は、キャリア形成・リスキリングセンターに登録することで、求職者へ、社員の育成、働きがい醸成に熱心な企業としてアピールすることができるようになっています。
ジョブ・カードとは
仕事や労働を通じた社会参画は、社会貢献に寄与するものでしょう。しかしながら保護者から、
“(いわゆる)有名大学に入りなさい!”とか、“手に職を得ていたら つぶしが利きやすい”といった、適性という、その人らしさ を踏まえないテキトーな職業能力開発が未だに世間では多く行われています。それでは手痛い停滞を続けるだけではないでしょうか。
その人の適性に応じた「キャリア」選好と、秩序だった支援が必要です。
生涯を通じ、その人らしい「キャリア」という職業志向性や方向性にのっとり、かつそこに向けて着実かつ確実な職業能力開発という投資を個別具体的に計画していくことと、修得してきた職業能力を記録するツールが必要です。それが「ジョブ・カード」です。
ジョブ・カードは以下の作成支援WEB/ソフトウェアを使って作成できます。
セルフ・キャリアドックとは
かつて、ある中堅企業で働く一人の社員がいました。毎日決まった時間に出社し、上司の指示に従って淡々と仕事をこなす。成果を上げても特に評価されることもなく、自分が何のために働いているのか、だんだんと分からなくなっていく——そんな「働かされている感覚」に支配された日々。
ところがある日、会社にキャリアコンサルタントがやってきました。「これからは“キャリアドック”という制度を導入します」と言うのです。社員一人ひとりが、自分の「キャリアアンカー」——つまり、働くうえで何を最も大切にしているのか——を見つめ直し、それを基にこれからの働き方やスキルアップの計画を、自分自身で描いていくという取り組みでした。
初めは半信半疑だった社員も、キャリアコンサルタントとの対話を重ねるうちに、ふと気づきます。「自分は“安定”を求めてこの職に就いたけれど、本当は“専門性”を高めて誰かの役に立ちたいと思っていたのかもしれない」。そこから彼の働き方は少しずつ変わっていきました。自ら学び、動き、役割を広げていく——かつての「死事」は、いつの間にか「志事」へと変わっていたのです。
こうした個々の気づきと成長を支える仕組み、それが「セルフ・キャリアドック」です。企業側もまた、将来に向けてどんな人材がどれだけ必要なのかというビジョンを持ち、教育訓練計画を立て、それに基づいて社員の能力を定期的に見直し、育成していきます。つまり、働く人と企業がともに未来を見据えながら、対話し、成長していく仕組みなのです。
そして——社員が主体的に働き、生産性が上がり、それが報酬や満足度の向上につながるとしたら。その先には、家計の安定、消費の拡大、そして日本経済の持続的成長といった大きなうねりも期待できるでしょう。
“働かされる”から“働きたい”へ。セルフ・キャリアドックは、そんな転換の起点となる取り組みです。
詳しくは、当社代表が監修したキャリアコンサルティングに活かせる 働きやすい職場づくりのヒント(金剛出版)をご覧ください。
これまでイヤイヤながら苦役・労役に従事していた労働者がいたとしても、セフル・キャリアドックを通じて主体的にそれぞれの「今」に適した職業に就きなおすと、「死事」が「志事」になります。つまりイキイキと働くようになると自然と生産性は上がることでしょう。
その生産性向上が賃金増になるならば、マクロレベルでは国民所得の増加と消費刺激に繋がり得ます。これらは「働き方改革」の目指す中長期的な潜在成長率向上に貢献することでしょう。